Core Web Vitalsとは?2025年のSEOで重要なUX指標
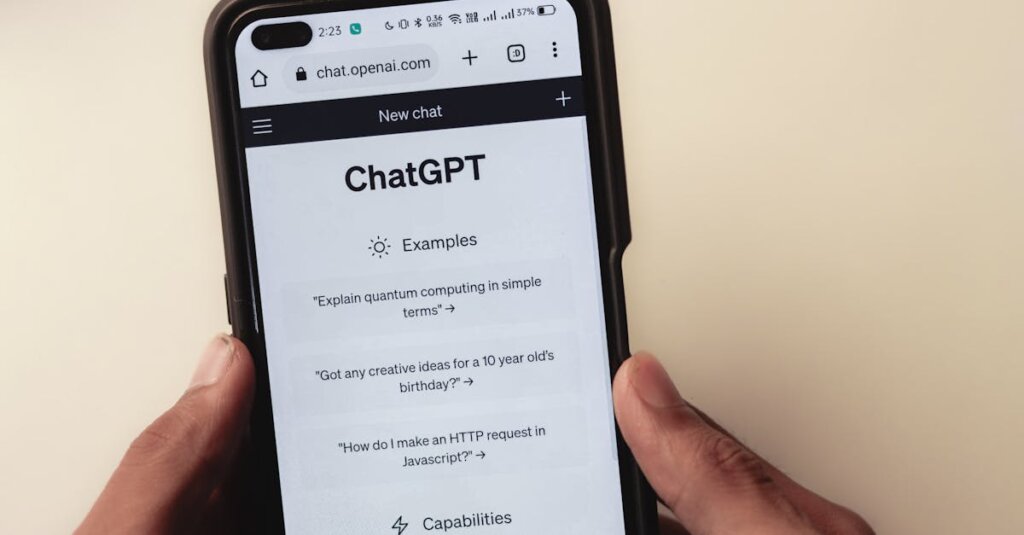
Core Web Vitalsとは何かをわかりやすく解説
Core Web Vitals(コアウェブバイタルズ)は、Googleがウェブサイトのユーザー体験(UX)を評価するために定めた一連の指標です。これらは単なる技術的なパフォーマンス指標ではなく、ユーザーが実際に感じるサイトの使いやすさや快適さを数値化するものとして注目されています。
具体的には、ページの読み込み速度、インタラクティブ性、視覚の安定性という3つの主要な要素を測定しています。これによりウェブサイトが「速く」「使いやすく」「見やすい」かどうかを評価し、検索エンジンのランキング順位にも影響を与えます。そのため、単にコンテンツの質だけでなく、サイトの技術的な品質やUXの高さもSEOにおいて重要視されるようになりました。
Core Web Vitalsが注目される背景には、スマートフォンやモバイルデバイスの普及により、ユーザーが快適に情報を得る体験の重要性が増したことが挙げられます。遅いページや操作がスムーズでないサイトはすぐに離脱されるリスクが高く、Googleもそのようなサイトを評価下げることで、質の高いユーザー体験を促進しようとしています。従って、これからのSEO対策ではCore Web Vitalsをきちんと理解し、改善することが必須となっているのです。
2025年SEOで求められる主要なCore Web Vitals指標と最新トレンド
2025年のSEOにおいて、Core Web Vitalsはますます重要な指標となり、特に3つの主要な要素が評価軸として注目されています。それがLCP(Largest Contentful Paint)、FID(First Input Delay)、CLS(Cumulative Layout Shift)です。これらの指標は、それぞれ異なる側面からユーザー体験の質を評価し、サイトのパフォーマンス改善に直結しています。
Core Web Vitalsの主要指標
LCP(Largest Contentful Paint)は、ページのメインコンテンツがどれだけ速く表示されるかを測ります。ユーザーがページを開いた際に見える最も大きな要素の読み込み完了時間であり、目安として2.5秒以内が理想です。遅いLCPは訪問者の離脱率を高め、SEOに悪影響を及ぼします。
FID(First Input Delay)は、ユーザーが初めてページ上で操作を行った際、ブラウザがその操作に反応するまでの遅延時間を示します。1秒以内が良いとされ、インタラクションのスムーズさを重視する指標です。遅延が大きいとユーザーのフラストレーションを招き、エンゲージメントの低下に繋がります。
CLS(Cumulative Layout Shift)は、ページの表示がどれだけ安定しているかを示す指標で、突然レイアウトがずれる視覚的な不快感の度合いを測ります。0.1以下が理想で、広告や画像の読み込みによるレイアウトのズレを抑えることが求められます。
2025年のSEO最新トレンド
2025年に向けて、Googleはこれらの指標をさらに厳格に評価し、モバイルファーストでのユーザー体験改善を促進しています。特にモバイルユーザーの増加に伴い、モバイル版ページのCore Web Vitalsは検索順位を左右する大きな要素となりました。
また、Googleのアルゴリズムアップデートでは、Core Web Vitalsの評価が従来以上に重視され、単なるコンテンツの質だけでなく、UX全体の質を包括的に評価する方向にシフトしています。これにはページの速度だけでなく、実際の使いやすさや視覚的安定性、インタラクションの快適さが含まれ、総合的なサイト体験の向上が必須です。
さらに、AI技術や機械学習の進展により、UXの個別最適化やパーソナライズが進むことも予測されています。これにより、Core Web Vitalsはユーザーごとの体験差をも考慮に入れた高度な評価指標へと進化していく可能性があります。
対策のポイント
2025年のSEO対策では、LCP、FID、CLSのそれぞれを細かく把握し、ページごとに数値改善に取り組むことが求められます。例えば、画像や動画の最適化、JavaScriptの効率化、レイアウトの安定化を意識した設計など、多方面からのアプローチが必要です。
結果として、Core Web Vitalsの改善はユーザー満足度を高め、離脱率を下げると同時に、検索エンジンからの評価向上につながるため、2025年のSEOにおける必須テーマと言えます。
内部対策としてのCore Web Vitals改善ポイント
Core Web Vitalsのスコア向上は、Webサイトの内部対策がカギを握ります。主にページ速度の改善、画像の最適化、そしてコードの軽量化がその中心となり、これらを適切に実施することでユーザー体験の質を大きく高めることが可能です。ここでは具体的に取り組みやすい改善ポイントを解説します。
ページ速度の改善
まず、LCP(Largest Contentful Paint)に直結するページの表示速度を上げることが重要です。サーバーの応答時間(TTFB:Time To First Byte)を短縮するために、高性能なサーバーの選定やCDN(コンテンツ配信ネットワーク)の導入が効果的です。CDNを使うことで、ユーザーの地理的な場所にかかわらず高速にコンテンツを配信できます。
また、不要なリダイレクトを避けることもポイントです。ページが多重リダイレクトしたり、過剰なAPI呼び出しがあると読み込み速度が悪化しLCPのスコアに悪影響を与えます。
画像の最適化
画像はWebページ内で大きな容量を占める要素の一つです。適切なサイズで最適なフォーマット(WebPやAVIFなど)を利用し、必要に応じて圧縮することで読み込み時間を大幅に削減できます。さらに、遅延読み込み(lazy loading)を取り入れることで、画面に表示される範囲に限定して画像を読み込む仕組みを導入すると、初期表示速度が向上します。
コードの軽量化と最適化
JavaScriptやCSSの最適化も欠かせない改善点です。特にFID(First Input Delay)に影響を与えるのがJavaScriptの処理時間で、不要なスクリプトの削減やコードの非同期・遅延読み込みを実装することで、ユーザーの最初の操作に対する反応速度を高められます。
また、CSSは必要なスタイルのみを抽出してインライン化したり、不要なスタイルを削除することで視覚の安定性を保ち、CLS(Cumulative Layout Shift)の改善につなげます。
レイアウトシフトの抑制
CLS改善のためには、広告や画像、動画などの動的要素が読み込み時にレイアウトを大きく変えないように、あらかじめ表示領域のサイズを指定することが効果的です。これによりユーザーが不意にスクロール位置を失うなどの不快感を減らせます。
実行しやすい改善フロー
改善策は一度に全てを完璧にするのではなく、PageSpeed Insightsなどのツールでスコアを測定し、ボトルネックとなる要素から優先して対応していくのがおすすめです。特にLCPはページ内で最も大きい要素に影響されるため、その要素(一般的にヒーロー画像やメインテキスト)の読み込みを優先させる工夫もポイントになります。
これらの内部対策はつまり「速く、安定して、スムーズな体験」をユーザーに提供し、Googleの評価基準に合致させるための基本的な手法です。2025年のSEOにおいては、Core Web Vitalsを意識したこれらの内部施策が成果の差を生む重要なポイントとなるでしょう。
外部対策とCore Web Vitalsの関係性
SEOにおける外部対策は、主に被リンクやサイテーション(言及)の獲得を通じてサイトの権威性や信頼性を高める施策です。一方でCore Web Vitalsはユーザー体験に関わるサイト内部のパフォーマンス指標であり、一見すると外部対策とは直接の関係が薄いように見えます。しかし、近年のGoogleのアルゴリズムアップデートを踏まえると、この二つは相乗効果を生み出す重要な要素として捉えるべきです。
外部評価とUX指標のリンク
被リンクはサイトの信頼性をGoogleに示す指標として古くから重宝されてきましたが、近年は単なるリンク数の増加よりも「質」がより問われています。質の高い被リンクは、ユーザーが実際に価値を感じるコンテンツに対して付与されるため、結果的に良質なUXが提供されているサイトへの評価が上がります。
ここでCore Web Vitalsが関連してくるのは、ユーザーが快適に利用できるサイト、すなわちページの読み込みが速く、インタラクションがスムーズでレイアウトが安定しているサイトは、ユーザー満足度が高まり自然な被リンク獲得につながる可能性が高まる点です。つまり、Core Web Vitalsの改善は被リンクの「質」を底上げする土台作りとも言えます。
被リンク品質向上のためのUX重視
例えば、外部メディアからのリンクやSNSでのシェアが増える案件は、ユーザー体験が良好であることが前提のケースが多いです。読み込みが遅い、操作がもたつく、レイアウトが崩れるといった問題があるサイトは、せっかく外部で紹介されてもユーザーの離脱率が高くなり、間接的にサイト評価に悪影響を及ぼします。
また、外部対策で重要な「サイテーション」でも同様です。ローカルビジネスや企業情報が一致し統一されていることに加え、Core Web Vitalsが高いレベルで保たれていれば、Googleからの総合的な評価はさらに高まります。
相乗効果を生む戦略
したがって、外部対策だけに頼らず、Core Web Vitalsを含むUX指標を意識したコンテンツ改善・技術改善をセットで行うことが効果的です。例えば、高品質な被リンクを得るために提供するコンテンツを高速かつ安定的に配信し、ユーザーがストレスなく閲覧・操作できる環境を整えることが挙げられます。
さらに、特定の業界での権威サイトやインフルエンサーからのリンク獲得の際には、Core Web Vitalsの数値や改善ポイントを示すことで、信頼感を与えやすくなるケースもあります。
SEO全体の最適化に向けて
結局のところ、2025年以降のSEOでは、外部対策による権威性の獲得とCore Web VitalsをはじめとするUX改善は切っても切れない関係にあります。優れたUXは質の高い被リンクの増加を促進し、良質な外部評価はGoogleにサイトの価値を強く認識させる――この好循環を意識した戦略設計が重要です。
これにより、単なる外部対策の強化に留まらず、ユーザー体験を最適化する「内×外」両面からのSEO施策が、確かな検索順位アップと持続的なサイト成長を支えることになります。
MEO(Googleビジネスプロフィール)とCore Web Vitalsの活用法
MEO(Map Engine Optimization)は、ローカルビジネスがGoogle検索やGoogleマップで地域ユーザーに目立つ存在になるための施策です。特にGoogleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)の活用は、地域検索で上位表示を狙ううえで必須となっています。ここにCore Web Vitalsの概念を組み合わせることで、より効果的なMEO対策が可能となるのです。
Core Web VitalsがMEOに与える影響
Googleはローカル検索結果のランキングにおいても、ユーザー体験を重視する方向へと進化しています。単に住所や営業時間の情報を掲載するだけではなく、リンク先のWebサイトやランディングページの質が順位に影響を及ぼすようになりました。特にCore Web Vitalsのスコアが良好なサイトは、検索者にとってストレスの少ない情報提供を実現しているため、高評価を得やすいのです。
たとえば、店舗の詳細情報や予約ページ、問い合わせフォームへのリンクが設置されたランディングページが、速くて快適に閲覧できることでユーザーの利便性が向上します。その結果、滞在時間や操作のスムーズさが改善され、Googleのアルゴリズムにおけるポジティブなシグナルとして働きます。
地域検索でのUX改善の具体策
MEOにおけるCore Web Vitals改善では、まずモバイルフレンドリーな設計が不可欠です。多くのユーザーはスマートフォンでローカル検索を行うため、モバイルの読み込み速度や画面レイアウトの安定性(CLS)に配慮したサイト作りが求められます。
また、店舗の魅力を伝える画像を最適化し、重要な情報がすぐに表示されるようLCPを意識してページ構成することもポイントです。フォームやボタンの反応が良く、遅延の少ないFIDも、問い合わせや予約のコンバージョン向上につながります。
Googleビジネスプロフィール活用時の注意点
Googleビジネスプロフィール自体は直接Core Web Vitalsのスコアに影響しませんが、プロフィール内の「ウェブサイト」リンク先がユーザーにとって快適な体験を提供できているかどうかは間接的に検索順位に響きます。したがって、プロフィール情報の正確性に加え、リンク先のサイトのUX改善に注力することが重要です。
さらに、口コミ対応や投稿を通じたユーザーエンゲージメントも地域評価には欠かせません。良好なユーザー体験を提供するWebサイトと結びつけることで、信頼性と利便性が高まり、他の競合店との差別化要因となります。
最新事例の紹介
近年、地域密着型の飲食店や小売業者が、Core Web Vitalsを改善したランディングページをGoogleビジネスプロフィールにリンクさせた結果、地域内での検索表示順位が向上し、来店数や問い合わせ数が増加した事例が報告されています。特にモバイルでの表示速度とユーザー操作の快適さを重視した施策が奏功しました。
このように、MEO対策とCore Web Vitalsは別々の施策に見えて実は密接に結びついています。地域検索での目立つ存在を目指すなら、Googleビジネスプロフィールの活用だけでなく、その先にあるウェブサイトのUX改善に注力することが成功のカギとなるでしょう。
Core Web Vitalsに関するよくある質問(FAQ)
Core Web VitalsはSEOやUX改善で注目されている指標ですが、実際の運用や対策においては多くの疑問や誤解が生じやすい分野でもあります。ここでは現場でよく挙がる質問をピックアップし、実務担当者が押さえておきたいポイントをわかりやすく解説します。
Q1: Core Web Vitalsはどのように測定すればいいですか?
Core Web Vitalsの測定にはGoogle提供の様々なツールが利用可能です。代表的なのは「Google PageSpeed Insights」で、URLを入力するだけでLCP、FID、CLSのスコアや改善提案が表示されます。また、Chromeブラウザのデベロッパーツール内「Lighthouse」や「Web Vitals拡張機能」も手軽に計測可能です。さらに、Google Search Consoleの「ウェブコアバイタル」レポートはサイト全体の問題を把握するのに役立ちます。
Q2: Core Web Vitalsの改善はどの指標から優先すべきですか?
改善の優先順位は、サイトの現状や主要なユーザー行動に応じて変わりますが、一般的にはLCPの改善が最優先です。これはページの主要コンテンツが速く表示されることが最もユーザーの満足度に直結し、離脱率の改善にもつながりやすいためです。次にFIDを改善し、最後にCLSの安定化に取り組むのが効率的な流れです。
Q3: Core Web Vitalsが悪くてもコンテンツが良ければSEOに問題はない?
良質なコンテンツは依然としてSEOの中核ですが、Core Web Vitalsの指標が低い場合、ユーザー体験の悪化が離脱増加や滞在時間の短縮につながるため、結果的にSEO評価も下がる可能性があります。Googleのアルゴリズムは総合評価で順位を決定するため、コンテンツとUXの両輪での最適化が必要です。
Q4: Core Web VitalsはPC版とモバイル版で異なる評価を受けますか?
はい、Googleはモバイルファーストインデックスを採用しているため、モバイル版のCore Web Vitalsがより重要視されています。実際、モバイル端末のネットワーク環境やデバイス性能の違いによりスコアが異なる場合が多く、モバイルでの改善に力を入れることが重要です。
Q5: CLS(レイアウトシフト)はどうやって改善すればいいですか?
CLSの主な原因は画像や広告、埋め込みコンテンツ等の読み込み時のサイズ指定不足です。改善には、レイアウト内での要素サイズを固定し、遅延ロードする広告や画像にも事前にスペースを確保することが有効です。また、動的に変わる要素の挿入は可能な限り抑えることも重要です。
Q6: Core Web Vitalsの改善はどのくらいで効果が出ますか?
改善の効果は施策内容やサイト規模にもよりますが、技術的な修正は数日~数週間で反映されることが多いです。Google Search ConsoleやPageSpeed Insightsで定期的に測定し、スコアの変化を確認しながら継続的に改善を行うことが望まれます。
これらはCore Web Vitalsに関する代表的なFAQですが、実際の対策ではツールの活用や現状分析をしっかり行い、段階的に改善に取り組むことが成功のポイントです。UXの質を高めることで、SEO効果だけでなくユーザー満足度の向上も図れるため、Core Web Vitalsは今後のWeb運営に欠かせない指標と言えるでしょう。
投稿者プロフィール

最新の投稿
 スタッフブログ2025-10-05DX導入から半年、何が変わった?──某定食チェーンの社内検証レポート
スタッフブログ2025-10-05DX導入から半年、何が変わった?──某定食チェーンの社内検証レポート スタッフブログ2025-10-03“ITリテラシー0”から始まった焼肉チェーンの業務効率化物語
スタッフブログ2025-10-03“ITリテラシー0”から始まった焼肉チェーンの業務効率化物語 スタッフブログ2025-10-01「もう紙の伝票には戻れない」──小さな回転寿司店のDX革命
スタッフブログ2025-10-01「もう紙の伝票には戻れない」──小さな回転寿司店のDX革命 スタッフブログ2025-09-29店長がDXを嫌がらなかった理由──現場主導で進める改革の裏側
スタッフブログ2025-09-29店長がDXを嫌がらなかった理由──現場主導で進める改革の裏側



